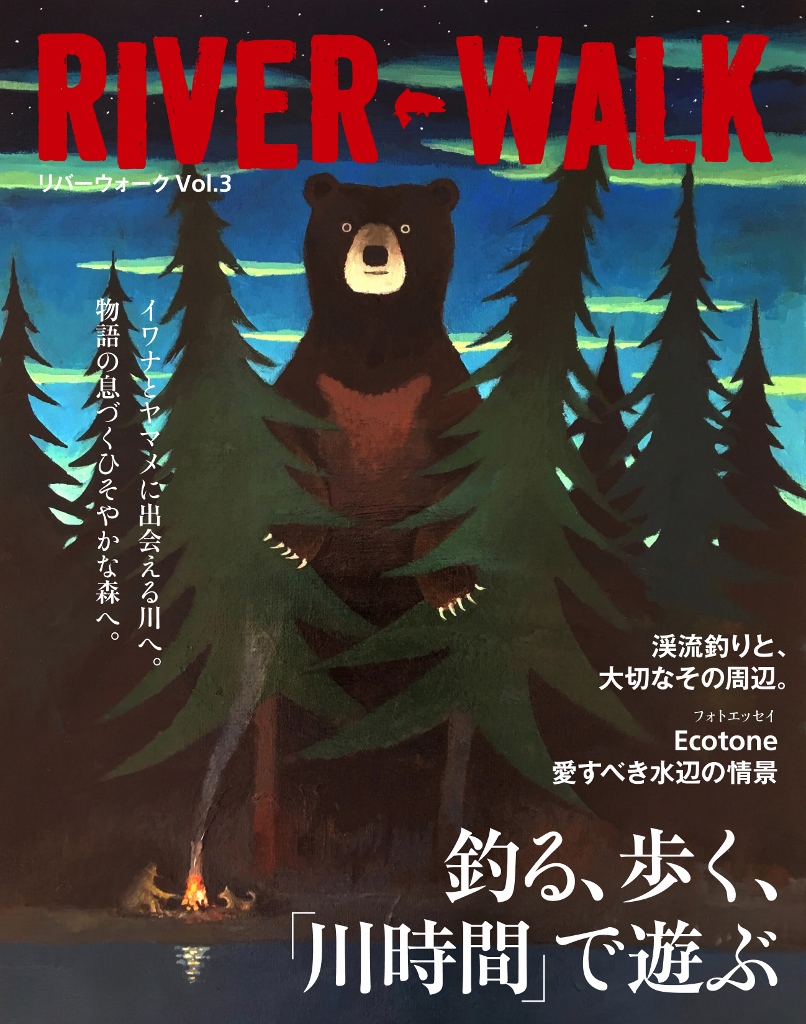ここ2週間ほど、毎朝の出勤途中に目的をもって川を歩いていました。
なにかといえば、なんてことはない、毎秋恒例の落ち鮎拾いです。
毎年、なにげなく川を歩いいて目に付いたところから始めていたのですが、今年は流下の始まりを目にしたいと思い、目を凝らしながら川を歩いていたのです。
昨年の初観察は10月17日でした。そして今年は遅れること1週間の本日、初めて観察することができました。

流れの緩む浅い溜まりに沈んでいました。死後硬直状態のメス(でしょうか?) 頭にはまだかろうじて黒いサビ色が残っていますが、大部分は色が抜け、黄金色になっています。18㎝ほどでしたでしょうか。臀ビレのあたりが擦り切れて少し骨が露出しているようにも見えます。おそらく産卵を終え、力尽きたものでしょう。
ここは埼玉南部の町なかの川っぷちですが、このアユは春に海から上がってきたものです。約30kmも川を上り、この川で夏を過ごし、産卵を終えて、この川を流れ下ります。卵から生まれた赤ちゃん(仔魚)はそのまま海まで一気に流されていくそうです。そして海で冬を越し、来年の春にはまたキラキラとした小さなアユたちが川を上ってくるのです。

立派な背ビレです。観察を済ませ、流れに戻しました。
実は今朝は、先にもう一匹のアユを拾っておりました。

こちらです。これもメスですが、まだ身体からはスイカのようなアユ独特の匂いを放っていました。こちらは体色を見る限り、まだ産卵前の様子。そして喉元が掻き切られていました。おそらく釣り人によるものでしょう。
この時期、川にはアユを求めて釣り人が並び、竿を振ります。落ち鮎拾いをしていると、毎年1、2匹はこのようなアユに出会います。ほとんどは小さくて痩せたもの。おそらく食べるのには向かないと判断したのか手荒く針を外した痕ではないかと思います。
焼けばきっと美味しいだろうと思い、一瞬「お持ち帰り」したくなりましたが、この後の予定を考え、これもそっと流れに戻しました。
アユの産卵は、これから12月中旬まで続きます。
生を全うしたアユの今際の美しさ。そしてこれらを求めて川辺にやってくるハシボソガラスやタヌキ、イタチの気配を追いながら、私も年末に向けて落ち鮎拾いを楽しみたいと思います。
ああ、もう年末かー。落ち鮎拾いは、私にとってなんだか心忙しくなる冬ごよみでもあるのです。□〈若林〉
【お知らせ】
川辺の自然観察をまとめた一冊、『武蔵野発 川っぷち生きもの観察記』発売中です。ニゴイの産卵行動についてとても詳しく書いていますので、ぜひご覧になってください(アマゾンの販売ページはこちら)