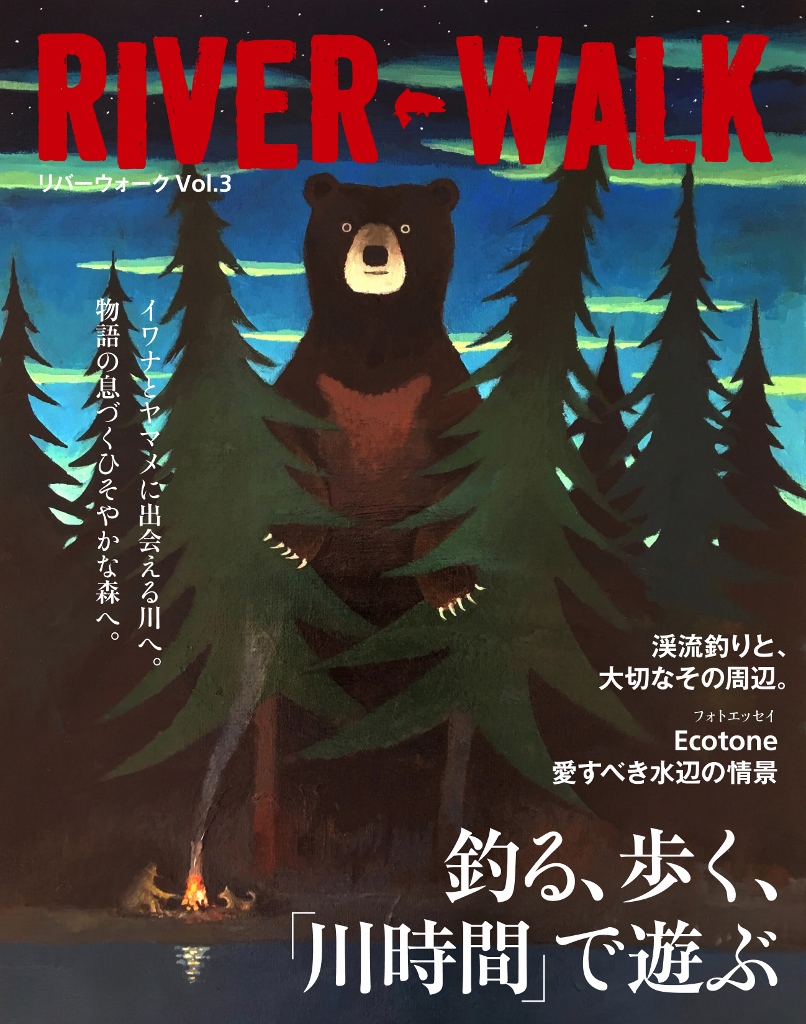昨日も今日も落ち鮎拾い。出勤前の日課となっています。昨日は雨あとで水温18.3℃、今日は北寄りの風の晴天で水温16.9℃。アユの産卵行動は、水温15℃を切るぐらいからが本番になるとのことですが、流下を観察した先週末から、今のところ毎日見ることができています。

見つけられるのはこんなところ。流れの巻いた「溜まり」となっている浅瀬です。ですが、こんなところは目立ちますから、動物たちも放ってはおかないでしょうけど。

こちら昨日観察したアユ。オスでしょうか・・。臀ビレでしか私は判断できないので欠損していると迷います。臀ビレあたりが擦れているのは産卵行動に参加した証だとは思いますので、全うしたアユと言えそうです。

浅瀬にもう一匹。

こちらは痩せた状態でした。体は擦れた箇所もありましたが、下アゴが欠けていたので釣り人に捨てられたアユかもしれません。

イタチに加えてタヌキの足跡も増えてきました。あくまでも個人的な妄想ではありますが、みんなアユを求めて集まってきているのではないでしょうか・・。

そして今朝は、ご覧のようなきれいなメスのアユが流下している姿を見ることができました。拾いあげると、まだかろうじて生きていました。外傷はなし。卵はまだお腹に残った状態。目が赤く染まり、少しだけ突出していました。冷水病の類かもしれませんが、それらしき症例もありませんでした。絶対美味しいだろうと思いましたが、時間的な余裕がなく川に戻します。
そして今日は、私的には初めてとなる、カルガモによる捕食行為を観察することができました。

慌ててカメラのレンズを向けましたが、撮影できたのはこの状態のみ。ですがこのカルガモは深さ60㎝ほどある場所で潜水をして、このアユを川底からくわえ上げました。1.8秒ほどは完全に潜った状態でした。カルガモもアユを食べるのですね。
大きすぎたのか、口に収まらず、最終的には離してしまいました。そこまで固執する感じではありませんでした。
で、流れ下ったアユを見ていると、今度はコイがスパスパと食べ始めたのです。

わかりづらいのですが、アユを横ぐわえしているところです。何度も何度も、30回ぐらいは口の中に入れたり出したりを繰り返し、段々とアユはふわふわになっていきました。少しずつ流下しながら捕食行為を繰り返していましたが、最終的に水深が浅くなりすぎたためか諦めて離れました。

状態を見てみたいと思い、長靴の喫水ギリギリアウトぐらいではありましたが、現場へ向かいます。

だいぶボロボロになっていますね。これはこれで、モクズガニやアメリカザリガニ、そしてミシシッピアカミミガメたちのご馳走になります。

結構大ぶりでした。メス・・かな?
満足して帰ろうとしたところ、「溜まり」にハシボソガラスの気になる動きを発見。アユをくわえているようでした。カラスは飛び立ち土手へ。普段から貯食行動を行っている場所なので、息を飲んで見守りましたが、ちょうど出勤に急いでいた女性がカラスの近くの土手を駆け上がり、残念ながら飛び立ってしまいました。その行先を追うと、川原へと・・。

まとめてくわえてるー。小型のアユでしょう。
残念ながら飛び去り川から離れてしまいました。
この時期の落ち鮎は、多くの動物を惹きつけます。
ハシボソガラス、カルガモ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、コイ、イタチ、タヌキ、そして私。
みんなアユが大好きなんですね。□〈若林〉
【お知らせ】
川辺の自然観察をまとめた一冊、『武蔵野発 川っぷち生きもの観察記』発売中です。ニゴイの産卵行動についてとても詳しく書いていますので、ぜひご覧になってください(アマゾンの販売ページはこちら)